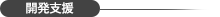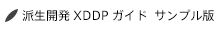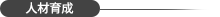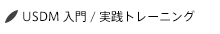![]()
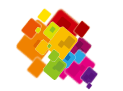
『XDDP』では、まず最初に「変更要求」に対する具体的な変更内容をとらえて、「変更要求仕様」として定義します。変更内容をとらえる方法としては、既存の機能仕様書などの資産から変更すべき内容を探し出す方法の他に、ソースコードから探し出す「スペックアウト」があります。「スペックアウト」とは理解したことと、拾い出した箇所、変更すべき項目を抽出して資料として残すことです。ここでとらえた変更内容を「要求」「仕様」に振り分けてUSDMに記述することで『変更要求仕様』として定義します。
既存資産の要求仕様書や設計書が整備されていて、「変更要求」が明らかであれば変更内容をとらえるのは容易です。しかし、それらがメンテナンスされておらず、ソースコードと乖離している場合もあります。そのような時にはソースコードを元に「スペックアウト」し、変更内容を探し出します。とはいえ、大量のソースコードに対して、やみくもに「スペックアウト」すると、いくら時間があっても足りません。「スペックアウト」は、変更箇所にあたりをつけてから実施します。
「スペックアウト」で、ソースコードを理解しながら「図面化」し、理解した箇所をチェックして進めていきます。図面化は構造と振る舞いに着目し、開発対象の特徴に合わせて構造図などの最適な図面を選択します。下図は構造図の実施例です。
.png)
「スペックアウト」で抽出したものも含めて、ここまででとらえた変更内容を元に、「変更要求仕様書」を『USDM』を使って作成します。『USDM』を作成する上で重要な点は「要求」と「仕様」を分けて書くことです。そうすることで、「要求」と「仕様」の関係が明確になり、仕様 のヌケモレや認識違いを防ぐことができます。その他、Before/Afterで記述する、変更の範囲・要求の理由を記述する、等のポイントがあります(詳細は「要求の定義と仕様化」をご覧ください)。
また、『USDM』で作成した「変更要求仕様書」は設計者に対する「作業指示」としても使えます。『USDM』では、仕様のモレや誤解を防ぐために、仕様を具体的に、検証可能なレベルで記載します。そうすることで、設計者に対して「厳密な変更の指示」が可能になります。「変更要求仕様書」が適切に作成されており、仕様通り変更作業を行えば、どんなスキルレベルの設計者であっても同じ結果になるはずです。